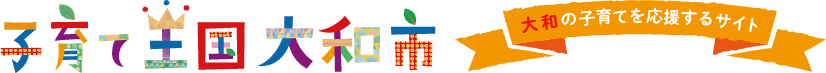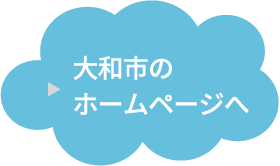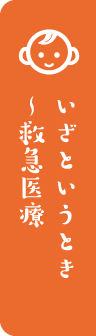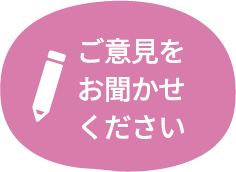未熟児養育医療給付
出生体重2,000グラム以下、または身体の機能が未発達なまま出生したため、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると認められたお子様の医療費(保険診療の自己負担分)と食事療養費(ミルク代)を給付します。
※健康保険適用外の差額ベッド代やおむつ代等は給付対象外です。
給付対象者
大和市に住民登録があり、次の1、2のいずれかにあてはまるお子様が対象となります。
1.出生時体重が2,000グラム以下
2.次のいずれかの症状がある
(1)一般状態
・運動不安・痙攣がある
・運動が異常に少ない
(2)体温
・体温が摂氏34度以下である
(3)呼吸器・循環器
・強度のチアノーゼが持続している
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
・呼吸数が毎分30以下である
・出血傾向が強い
(4)消化器
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便がある
(5)黄疸
・生後数時間以内に黄疸が発生する。又は異常に強い黄疸がある。
給付期間
指定養育医療機関に入院して養育医療を開始した日から退院するまでの期間で、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
※出生時から一度も退院していない場合に限ります。
申請方法
次の書類を、子ども医療費助成事業医療証交付申請の書類とあわせて、保健福祉センターこども総務課に提出してください。
【下記書類の①~③はこちらからまとめてダウンロードできます(PDF)】 【記入例】
① 養育医療給付申請書
記入は、保護者が行ってください。
② 世帯調書
記入は、保護者が行ってください。
③ 養育医療意見書
指定養育医療機関の医師に依頼し、発行してもらってください。
④お子様が加入する健康保険の資格情報がわかるもの
加入する医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」を印刷したものなど
※マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)では手続きはできません。
※郵送申請の場合はコピーを添付してください。
⑤ 申請者、来庁者の本人確認書類(以下のいずれか1つ)
顔写真付きの証明書類1点、または、顔写真のない証明書類2点
※1つの書類で本人確認が可能なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。
※2つ以上の書類で本人確認が可能なもの
基礎年金番号通知書又は年金手帳、住民票など
※郵送申請の場合はコピーを添付してください。
⑥ 照会同意書(PDF)【記入例】
※お子様と同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分が必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)市外在住の扶養義務者については、本人確認書類とマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)のコピーを添付してください。
※大和市で対象課税年度の課税をされている方は不要です。
・対象課税年度は次のとおりです。
申請月が4月~6月の場合・・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)
申請月が7月~3月の場合・・・・当年度(前年度の所得に対する課税)
※マイナンバーを利用した地方税関係情報の照会結果によっては、対象課税年度の課税(非課税)証明書を提出していただくことがあります。
※照会同意書をご提出いただけない方はご相談ください。
変更の届出の提出
申請時点から次のとおり状況が変わった場合は、お手続きが必要となりますので、保健福祉センターこども総務課にご連絡ください。
① 治療期間が延びる場合
② 転院する場合
③ 住所や健康保険の資格情報が変わった場合
給付方法
申請してから2週間ほどで養育医療券を発行します。医療機関での受診の際に、窓口で提示してください。医療費(保険診療)と食事療養費(ミルク代)が助成されます。
なお、医療券提示前に医療機関で支払いを済ませてしまうと、払い戻しはできませんので、ご注意ください。
自己負担金
養育医療に対する医療費については、市が医療機関に支払いますが、その世帯の対象課税年度の市町村民税額等に応じて自己負担金が発生します。大和市の医療費助成(子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成など)を受けている方は、養育医療の自己負担金を医療費助成から充当させていただきますので、保護者の方が自己負担金を支払う必要はありません。
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
● このページに関するお問い合わせはこちら