子育て支援制度
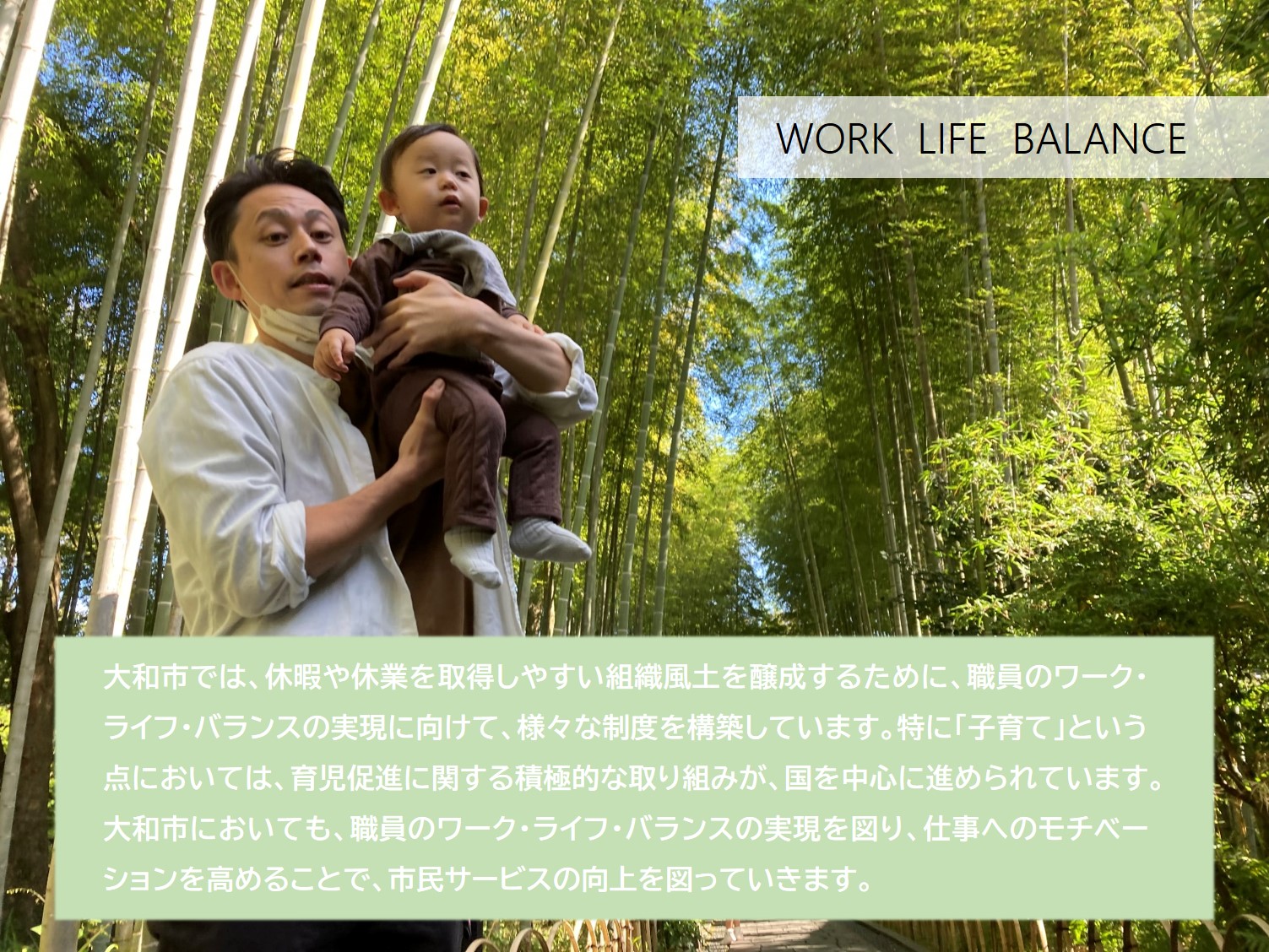
出産・育児に関する制度 ※一部をご紹介します
出産休暇
出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産日の翌日から8週間目にあたる日まで出産した女性職員が取得できる休暇
出産補助休暇
配偶者の出産に伴う、出産時の付き添いや入院中の配偶者の世話、出生届の提出などを理由に、3日間の範囲で取得できる休暇
育児参加休暇
配偶者の出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合14週間前)の日から、出産の日から1年目にあたる日まで、出産に係る子または小学校就学前の上の子の養育のため、5日間の範囲で取得できる休暇
育児休業
子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)まで、育児休業を取得可能
※取得は原則2回まで。それに加えて、子の出生の日から57日以内に「産後パパ育休」が2回まで取得可能。
部分休業
小学校就学前の子を養育する場合、1日を通じて2時間を超えない範囲内で部分休業が取得可能
子の看護休暇
子が満9歳になる日以後の最初の3月31日までの期間において、子の看護が必要である場合、年度において5日間(対象の子が2人以上の場合は10日間)の範囲で取得できる休暇
子育て支援制度の周知・意識啓発について
子育て支援制度のさらなる周知と意識啓発に向けて、職場全体で育児を応援し、希望する職員が適切に育児に係る休暇・休業を取得できる体制を整えることを目的とし、以下の取り組みを実施しています。
イクボス宣言
組織全体として、職員が業務と子育てを両立できる環境を提供する取り組み。
「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司のことを指します。
少子高齢社会という大和市にとどまらず国全体の喫緊の課題を解消するためには、ワーク・ライフ・バランスの充実を支援しながら、職員の能力を十分に発揮できるような労働環境を整備することが求められています。
育児応援相談制度
妊娠中の職員又は配偶者が出産することとなった職員について、所属長が「子育て支援ガイド」を活用して、育児に係る制度等を説明したうえで、本人の意向を確認しながら、一緒に育児休業等の計画(「育児に係る休暇・休業制度取得計画書」)を作成します。
職場全体で育児を応援し、希望する職員が適切に育児に係る休暇・休業を取得できる体制を整えることを目的としています。
男性職員の育児応援プロジェクト
男性の育児は、子育てをしたいという男性の希望を実現するだけでなく、パートナーである女性に偏りがちな育児や家事の負担を分かち合うことで、女性の活躍促進にもつながります。また、休暇や休業を取得しやすい組織風土を醸成することは、全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現にもつながります。
男性職員のさらなる育児休業の取得促進を図るために、以下の取り組みを実施しています。
育休制度に係る研修会の開催
研修会(動画による研修等)を開催し、大和市の育児休業制度の周知を図っています。
育休等啓発ガイドブックの発行
令和4年10月に、「職員の育児・介護のための 両立支援ガイドブック」を全職員向けに作成しました。ガイドブック内には、管理職(所属長)が担うこと、各種制度の詳細についてなど、育児に対する不安や悩みなどを解消していただくために、詳細に記載しています。
育休取得モデルケース(収入)の提示
両立支援ガイドブックと同時期に「男性職員向けの育児応援リーフレット」も作成。育児に係る各種制度の詳細を中心に、実際に育児休業を取得した男性職員のインタビューや、育児休業取得期間中の給与シミュレーションなどを記載しています。
育児休業取得者の声
「子育て」という点において、育児促進に関する積極的な取り組みを大和市においても推し進めている中で、実際に育児休業を取得した職員に取材をしましたので、ワーク・ライフ・バランスを実現している職員の声をぜひ聞いてください。
<インタビュー内容>
■育児休業を取得する際の周囲の反応・サポートについて
■育児休業を取得してよかったこと・嬉しかったこと
■仕事と育児の両立(復帰後の働き方など)について
■育児休業取得中の「1日のスケジュール」
■育児休業復帰後の「1日のスケジュール」 など


更新日:2024年07月23日