高座海軍工廠と台湾少年工(2)
日本行きの決心
当時の台湾では主要な仕事はすべて日本人が占め、仕事もなく生活の展望が見いだせない状況でしたが、募集に応じたのは、5年後には上級学校の卒業資格がもらえて、台湾に帰れば技術者として就職できるという募集の条件を信じたからと思われます。
少年工たちの暮らし
現在の大和市上草柳地区にあった寄宿舎で暮らしていました。彼らのここでの生活と労働は過酷で、特に日本の寒さと食糧不足は深刻でした。しかし、月2回あった休みには買い物をしたり、江ノ島に遊びに行ったり、中には新宿まで行ったと証言している人もおり、楽しかったという証言もあります。生活の全般は年少者が大半であったため、年長者の台湾の中学校卒業生たちが世話をしていました。

寄宿舎の食堂

寄宿舎の風呂場
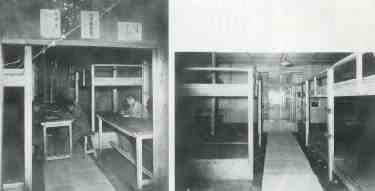
寮の自習室(左)と室内

寮から朝の出発

給料の支給

寮の窓
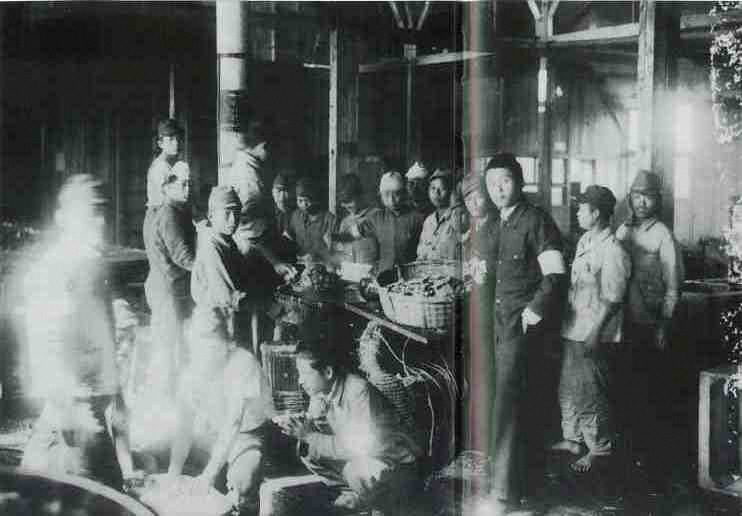
寮の炊事場
少年工たちの教育
特に重視されたのは、日本人になりきるという「皇民化」教育でした。神社の参拝は言うに及ばず、日本の風習に慣れるような訓練が行われました。また、何よりも日本語が重視されました。
少年工の犠牲者
8千余人の台湾の少年工たちが長い人で3年近くの間、戦時下の日本にいたため、犠牲者も多く出ました。そのうち大和市内関係のものとしては、1945年7月30日に市内上草柳の山林での空襲があげられます。夜明けで工場から寄宿舎に帰る途中を狙われたもので、6名が犠牲となりました。この他10名が死亡し、これらの犠牲者の供養のために、1963年11月、市内上草柳の善徳寺の境内に「台湾戦没少年の慰霊碑」が建てられました。

善徳寺

本 殿


善徳寺境内に建立されている「戦没台湾少年の慰霊碑」


帰 国
各地で終戦を迎えた少年たちは、市内上草柳の寄宿舎に次々と送り返され、寄宿舎は少年たちで一杯になりました。少年たちは年長の指導者を中心に、役割分担をしながらまとまって整然と集団生活をしました。1946年1月横浜から乗船した少年たちの第1陣は、遺骨と負傷者およびその付添い人たちを乗せて無事に台湾に到着しました。一部に残留者がいたものの大半は帰国しました。
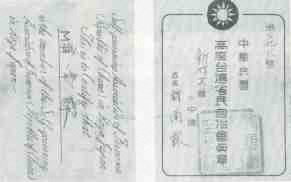
←高座台湾省民自治会員章
日本の敗戦以降1946年1月に帰国するまでの間、台湾少年工員たちは自治組織を設立し、警備など各種業務を分担した。
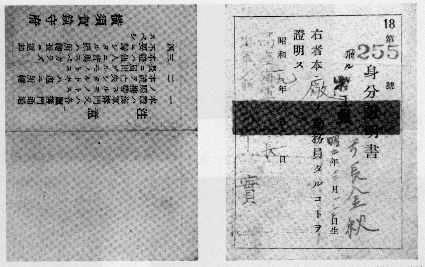
←高座海軍工廠身分証明書 (右=表面、左=裏面)

←帰国船
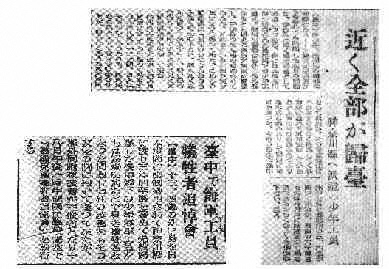
←台湾日日新報記事
右=1946年(昭和21年)1月9日付け
左=1946年(昭和21年)1月17日付け
その後の少年たち
帰国した少年たちのごく一部は「高座海軍工廠工員養成所見習科」の卒業証書を国から受け取ったものの、多くの人たちはそれさえもなく、その後自国の言葉をもう一度学び直したり、職業を得るのに大変な苦労をしました。しかし戦時下の苦労を共にしてきたことをなつかしく思い、高座会を結成し、その中には今でも当時交流した日本人との関わりを大切にして、手紙や直接会うなどして交流を深めている人たちもいます。
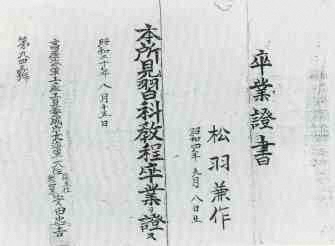
卒業証書
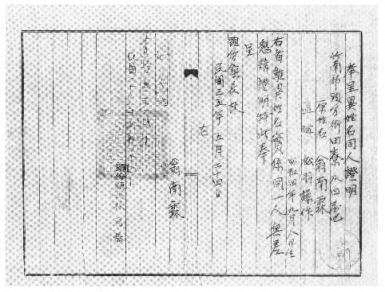
異姓名同人証明書 1946年5月
高座海軍工廠への入廠を契機に、少年たちは改姓名を使用したが、帰国後に「原姓名」と「通称」が同一人であることを証明したもの。




更新日:2024年05月21日