戦中・戦後の人々の生活の様子(3)
昭和16年(1941年)頃~終戦

勤労奉仕
中学生が農村の出征軍人留守家族の家へ勤労奉仕に来たときの様子。オカブ(陸稲)の草取りを手伝っています。

勤労奉仕
休憩の様子。農作業の合間におやつを食べています。生徒たちは3日間程手伝いに来たそうです。

深見島津青年団のサツマ芋掘り
青年団の畑にて。現在の大和自動車学校付近。

林間での葬儀

水道
鶴間台では、昭和25~26年頃に水道が設けられたそうです。共同利用だった屋外の水道での水仕事。
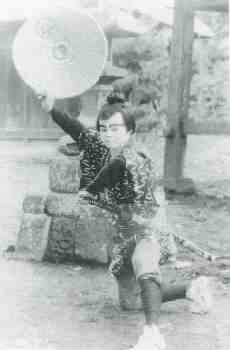
素人演芸
上和田左馬神社にて衣装を着て記念撮影

鶴間台での子供会発表会国旗掲揚式
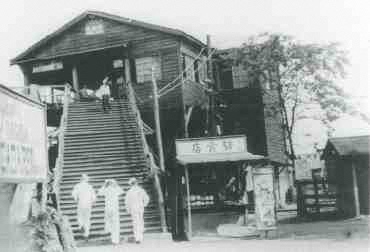
大和駅舎
昭和33年6月22日に焼失するまでの駅舎です

野辺の送り
下鶴間代官山で行われた、出征し戦死した人の葬式の野辺の送り。戦後になり、戦中に行われた戦死者の村葬とは異なりしめやかに行われました。葬列は先頭よりタツノクチ、ハタ、遺骨、花輪、カネ、坊さん(鶴林寺)と続いています。葬列の歩く道は座間・大和線です。

祭り
大和天満宮の祭りで、銀座通り中程を子ども神輿がねり歩いているところ

成人式
上草柳青年団倶楽部前での記念写真
「大和写真館」および「大和写真館2」より



更新日:2022年02月01日