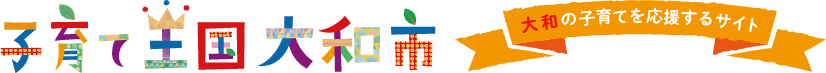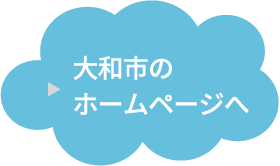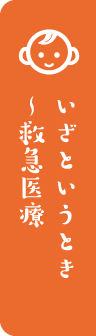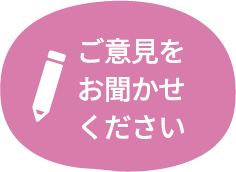子ども医療費助成
大和市に住民登録をしている高校卒業相当年齢までの児童が、病気やケガなどで医療機関にかかった際に、保険診療で支払う医療費の自己負担分を助成します。
また、ひとり親家庭等の方については、先に ひとり親家庭等医療費助成 の項目をごらんください。
医療費の助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。申請書と必要書類をあわせて提出してください。
医療機関などの適正受診にご協力ください
必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関における適正な受診についてご理解とご協力をお願いします。適正受診について
助成対象
0歳から高校卒業相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童
助成対象の要件
次の4要件すべてを満たしている方。
① 大和市に居住し、住民登録をしている。
② 健康保険に加入している。
③ 他の公費医療費助成を受けていないこと(生活保護、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度等)。
④ 児童福祉法に基づく措置による医療を受けていないこと。
保護者の所得の確認について
保護者の所得制限はありませんが、県への補助金の申請のため、毎年児童の誕生月に所得の確認を行っています。転入や未申告等により、大和市で保護者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要となる場合があります。
※ 確認する所得年度について
児童の誕生月が1~ 6月:児童の誕生月の前々年分の所得
児童の誕生月が7~12月:児童の誕生月の前年分の所得
市外から転入された方は、転入月により対象年度が異なります。
申請方法
子ども医療証交付申請書に必要事項を明記し、次の必要書類を添付してください。手続きは、持参(こども総務課、市民課、各分室)、郵送(こども総務課宛て)、電子申請、いずれかの方法により可能です。
② 対象児童の加入健康保険が確認できる書類のコピー
・資格確認書(お子様のもの)、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの等
(お子様の個人番号および加入健康保険欄の記載をされている方は省略可)
③ 申請者の本人確認書類をコピーしたもの
申請者は、保護者のうち、所得が高い方となります。窓口に来られた方が申請者ではない場合は、来庁された方の本人確認書類と代理権を確認するための書類のいずれも必要となります。
④ 児童が外国籍の方の場合は、児童の在留カード等をコピーしたもの
⑤ 保護者が市外在住者の場合は、保護者のマイナンバーや住所が分かるものをコピーしたもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票 ※高校卒業相当年齢の児童の保護者のマイナンバーは不要です)
※ 本人確認書類とは:顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)1点もしくは、顔写真なしの証明書(基礎年金番号通知書又は年金手帳、住民票、資格確認書(申請者のもの)など)2点。※ 代理権を確認するための書類とは:申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど(いずれもコピーしたもので可)
電子申請はこちら
郵送の宛先
〒242-8601
大和市鶴間一丁目31番7号(大和市保健福祉センター2階)
大和市役所 こども総務課 手当医療係 宛
子ども医療証の更新
子ども医療証は、児童の誕生月(1日生まれの場合は、誕生月の前月)に原則自動で更新されますので、お手続きは不要です。有効期間を更新した新しい医療証は、毎月15日前後に発送しますので、当月下旬頃にお手元に到着予定となります。
※月末を迎えても新しい医療証がお手元に届かない場合は、こども総務課へご連絡ください。
子ども医療証の使用方法
・病院や薬局の窓口で、マイナ保険証等とともに子ども医療証を提示してください。神奈川県内の医療機関等では、保険診療の自己負担分が助成されます。
なお、助成されるのは保険診療にかかる自己負担分のみとなり、健診や予防接種など保険適用外(自費)の診療は対象となりません。また、加入している健康保険が神奈川県外の国民健康保険組合等の場合や、神奈川県外の医療機関等を受診した場合は、お渡ししている子ども医療証は使えないため、後日市へ払い戻しの申請をしてください。
・交通事故など第三者行為によるケガ等の医療費は原則、その加害者が負担すべきものです。受診の際は、子ども医療証を使用しないようにお願いいたします。
学校等でのけがなどについて
学校管理下(授業中、登下校中、部活動中など)で発生した児童生徒の負傷等に対して、医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」という制度があります。
学校管理下での負傷等した場合は医療証を使用せず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。一時的に窓口で自己負担額を支払っていただきますが、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
なお、「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、以下の方法で申請をしていただくことで、医療費の自己負担分を払戻します。
⇒申請方法、制度の詳細はこちら【学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)】
また、上記以外にも私立学校、高校、保育所、幼稚園、スポーツクラブチーム等での負傷等は、各施設、所属団体で加入の保険(医療費の自己負担額が給付されるもの)が優先され、子ども医療費助成の対象外となりますので、医療証は使用できません。詳細は各施設、各団体等へお問い合わせください。
子ども医療証を使わずに医療費を支払った場合(県外で受診した場合など)
神奈川県外の医療機関を受診した場合や、子ども医療証を提示せずに保険診療を受けた場合などは、受診した月の翌月以降に、保健福祉センター2階こども総務課で払い戻しの申請をしてください。審査を行ったうえで、後日、指定の口座に振り込みます。
なお、給付を円滑に行うため、受診した月の翌月から1年以内にご申請いただきますようお願いします。領収日翌日から5年が経過すると時効となって申請できなくなるのでご注意ください。
※ 市への助成申請を行う前に、加入している健康保険組合等に療養費の給付申請が必要な場合などは、申請期限が2年以内となる場合がありますのでご注意ください。
申請日
受診した月の翌月以降
申請する場所
大和市保健福祉センター2階こども総務課
持ち物
① 申請者の本人確認書類(★1)
※申請者は、保護者のうち、所得が高い方となります。窓口に来られた方が申請者ではない場合は、来庁された方の本人確認書類(★1)と代理権を確認するための書類(★1)のいずれも必要となります。
② 申請者名義の通帳やキャッシュカード
③ 子ども医療証
④ 受診時の領収書の原本もしくは原本証明(領収書は、受診者氏名・保険点数・診療日・金額・医療機関名が記載されたもの)
⑤ 高額療養費支給決定通知書または家族療養附加給付金支給決定通知書(該当した場合のみ)
★1(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※申請の際は、対象児童の加入健康保険が確認できる書類のご持参をお願いいたします(コピーでも可)。
(例)資格確認書(お子様のもの)、資格情報のお知らせ等
※ 医療費が1件あたり2万円を超えた場合は、⑥の対象となる場合があります。対象かどうかは、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
※ マイナ保険証等を提示せず医療費を全額負担(10割)した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。
※ 補装具(治療用メガネ、インソール等)を医師の指示で作成した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書、医師の診断書・指示書の原本(原本証明可)が必要となります。
※ 国の公費負担医療の医療券(小児慢性特定疾病医療費や自立支援医療など)をお持ちの場合は、受給券や管理票が必要となります。
※ 子ども医療費助成制度で助成を受けた(または助成を受ける見込みがある)医療費は、自己負担がないため、税法上の医療費控除の対象とはなりません。
子ども医療費助成制度に関する手続きができる窓口
-
こども総務課、市民課、渋谷分室、中央林間分室でできる手続き
交付申請、再交付申請、住所変更、加入している健康保険の変更、子ども医療証の返却
-
こども総務課のみでできる手続き
子ども医療証の氏名の変更、子ども医療証を使わずに医療費を支払った場合の払い戻しの申請
子ども医療費助成制度に関する手続きは、土・日曜日、祝日と年末年始を除き、次の窓口で申請することができます。ただし、内容によってはこども総務課のみでの受付となる場合があります。
郵送・電子申請が可能な手続き
交付申請
記入見本[PDF(497KB)]をごらんになりながら、必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送してください。
電子申請は こちら
健康保険の変更手続き
記入見本[PDF(120KB)]
をご覧になりながら、必要事項を記入し、申請者の本人確認書類及び対象児童の加入健康保険が確認できる書類(資格確認書および資格情報のお知らせ等)のコピーと
一緒に郵送してください。
※対象児童の個人番号および加入健康保険欄の記載をされている方は省略可
変更届[PDF(88KB)]
電子申請はこちら
住所変更(市内転居)の手続き
市内で転居された際に新住所の医療証を交付するための手続きです。
記入見本[PDF]をごらんになりながら、必要事項を記入し、申請者の本人確認書類と一緒に郵送してください。
電子申請はこちら
医療証の再交付申請の手続き
子ども医療証を破損し、汚損し、または紛失した際に再交付をするための手続きです。
記入見本[PDF]をごらんになりながら、必要事項を記入し、申請者の本人確認書類と一緒に郵送してください。
電子申請はこちら
子ども医療証の審査に必要な同意書の提出
(高校生相当年齢の児童について申請する場合、同意書は省略することができます)
本人が必要事項を記入し、添付書類をつけて郵送してください。
同意書([PDF])
電子申請はこちら
不足書類の提出手続き
既に新規等の申し込みをなされた方で、現在保留となっており、不足書類を提出するための手続きです。
電子申請はこちら
期限切れや、市から転出したことで使えなくなった子ども医療証の返却
適正受診について
- かかりつけの医師を持ちましょう
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。 - ジェネリック医薬品を利用しましょう
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効果・効能を持ち、価格が安く設定されています。 - やまと24時間健康相談を利用しましょう
看護師等の資格を持った相談員による、24時間体制の電話健康相談を実施しています。
専用電話番号:0120-244-810(通話料無料)
※この事業には特定防衛施設周辺整備調整交付金が一部充当されています。

防衛省(調整交付金事業)
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
● このページに関するお問い合わせはこちら