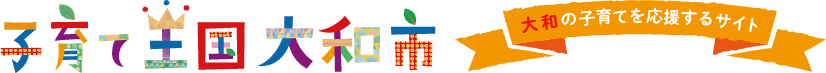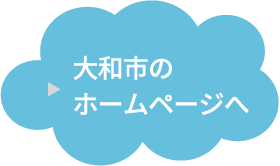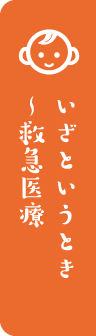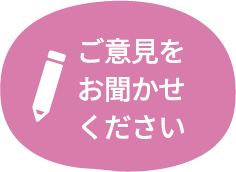保育所・幼稚園入所までの流れ
5.幼稚園の入園申し込み(無償化認定)について
「令和8年度大和市幼稚園利用ガイド」参照
幼稚園の利用について
保育料の無償化
●教育時間の無償化
●預かり保育の無償化
●副食費の無償化
無償化の手続きについて
幼稚園の利用について
大和市の幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)(以下、幼稚園等といいます。)は全て民間の施設です。各幼稚園等の特徴・利用条件・実費負担等については、直接、幼稚園等に確認してください。
(1)入園の手続き
①幼稚園等の利用を希望する場合は、利用を希望する幼稚園等に事前に連絡して見学を行い、利用条件
や実費負担等を確認してください。
②願書は例年10月15日から各幼稚園等で配付されます。利用を希望する幼稚園等から受け取り、幼稚
園等が指定する期限までに提出してください。
③無償化に関する書類は、市のホームページまたはほいく課窓口若しくは幼稚園等から受け取り、利用開
始前までに幼稚園等を通じて提出してください。
(2)預かり保育について
幼稚園等では預かり保育(教育時間の範囲外でお子さんを預かること)を実施しています。利用方法や利用料については、直接、幼稚園等に確認してください。なお、預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、月64時間以上の就労等の理由により大和市から保育の必要性の認定を事前に受ける必要があります。
保育料の無償化
幼稚園等の保育料については、無償化の対象になるものがあります。項目としては、「教育時間の無償化」と「預かり保育の無償化」、「副食費の無償化」の3つがあります。それぞれについて金額と条件が異なります。
教育時間の無償化
無償化の認定を受けた方が、幼稚園等の教育時間の無償化の対象になります。
後述する預かり保育の利用料の無償化・副食費の無償化とは異なり、認定の条件はありません。
幼稚園等に通園する全ての3~5歳のこどもが対象です。3歳になった日から無償化、助成の対象となります。
※保育料とは別に、実費として徴収される通園バス代や行事費等は、無償化の対象とならずに保護者負
担になります。
①無償化の金額
| 新制度幼稚園 認定こども園(幼稚園機能部分) |
私学助成幼稚園 ※㋐、㋑のうちいずれか低い額 |
|
|---|---|---|
| 1月当たりの無償化の金額 |
保育料は無料 |
㋐25,700円(上限額) |
②無償化給付の請求手続き
無償化の金額は大和市から幼稚園等に給付しますので、大和市に対する無償化給付の請求手続きはありませんが、教育時間の保育料を全額支払っている場合は、幼稚園等の指示に従って手続きを行ってください。
預かり保育の無償化
保育の必要性の認定を受けた方が、預かり保育を利用した場合に無償化の対象になります。
※満3歳児は、市民税均等割非課税世帯、生活保護世帯、里親またはファミリーホーム(以下、里親等。)に
委託されている場合 のいずれか(以下「非課税世帯等」)で、かつ、保育の必要性の認定を受けた方が対
象です。
保育の必要性についてはこちら
①保育の必要性の認定(ふたり親世帯の場合には、父母ともに保育の必要性があることが必要です。)
| 保護者の状況 | 利用できる期間 |
|---|---|
|
自宅内外で月64時間以上働いているとき |
小学校就学前まで |
|
出産の準備や出産後の休養が必要なとき |
産前6週(多胎の場合は14週、産前6週目の日以前に産前休暇が開始となる場合は、効力発生日)から産後8週を含む月
|
|
病気、負傷、障がい等のため保育が困難なとき |
医師の診断書等で必要と認める期間 |
|
介護や看護を64時間以上しているとき |
医師の診断書等で必要と認める期間 |
|
震災、火災などの復旧にあたっているとき |
復旧状況により必要と認める期間 |
|
大学などに月64時間以上通っているとき |
通学期間 |
|
仕事を探しているとき |
原則として3か月 |
|
育児休業(育児・介護休業法規定の育児休業に限る。)開始前から預かり保育を利用し、育児休業中も継続利用するとき |
育児休業が終了する日の属する月の月末まで |
②無償化の金額
| 3~5歳児 | 満3歳児(非課税世帯等) | |
|---|---|---|
| (ア)(イ)のうち低い金額 |
(ア)450円×1月当たりの預かり保育利用日数 (イ)1月当たりの預かり保育の利用料 |
|
| 1月当たりの上限額 |
11,300円 |
16,300円 |
③幼稚園等と無償化対象の認可外保育施設等を併用している場合
原則、教育時間外に利用した認可外保育施設等は無償化の対象外になりますが、預かり保育を実施していない幼稚園等や預かり保育が一定基準未満(1日8時間未満又は年間200日未満)の幼稚園等を利用している場合は、預かり保育と認可外保育施設等の利用分を合わせ、②の範囲で無償化の対象になります。
④無償化給付の請求手続き
預かり保育の利用料の無償化の金額は大和市から幼稚園等に給付しますので、大和市に対する無償化給付の請求手続きはありませんが、預かり保育の利用料を全額支払っている場合は、幼稚園等の指示に従って手続きを行ってください。併用した認可外保育施設等の利用分が無償化の対象になる幼稚園等に在籍していて、認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設等の利用料については大和市に対する無償化給付の請求手続き(請求書・認可外保育施設等が交付した領収証・提供証明書の提出)が必要になります。
| 認可外保育施設等の利用月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 請求期日 ※土日祝日のときは翌開庁日 |
7月25日 | 10月25日 | 1月25日 | 4月25日 |
| 給付予定日 | 8月末 | 11月末 | 2月末 | 5月末 |
⑤施設等利用費(認可外保育施設等利用時の利用料)の請求の時効について
施設等利用費(認可外保育施設等利用時の利用料)利用の請求の時効は2年です。(大和市での認定を受けていない期間は請求できません。) 時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご提出ください。(次の例をご参考ください。)
| 請求対象月 | 市受付日(郵送の場合、消印日) | 請求可否 |
| 令和5年5月分 | 令和7年5月1日 | 可 |
| 令和7年5月31日 | 可 | |
| 令和7年6月1日 | 不可 |
請求書等の書式についてはこちら
副食費の無償化
無償化の認定を受けた方が、①の要件に該当する場合は、おかず等の副食費が無償化の対象になります。
※米・麺・パンなどの主食費は無償化の対象外です。
①無償化の要件(次のいずれかに該当する場合は無償化の対象になります。)
|
1 |
保護者(単身赴任等で別居中の方を含む)の市民税所得割額の合算額が77,100円以下の場合 |
|
2 |
幼稚園等を利用するお子さんが第3子以降の場合 |
|
3 |
生活保護世帯の場合 |
|
4 |
幼稚園等を利用するお子さんが里親等に委託されている場合(措置委託通知書のコピーの提出が必要。) |
②無償化の金額
| 新制度幼稚園 認定こども園(幼稚園機能部分) |
私学助成幼稚園 ※㋐、㋑のうちいずれか低い額 |
|
|---|---|---|
| 1月当たりの無償化の金額 |
副食費は実費負担が免除 |
㋐4,900円(上限額) |
③無償化の請求手続き
無償化の金額は大和市から幼稚園等に給付しますので、大和市に対する無償化給付の請求手続きはありませんが、副食費を全額支払っている場合は、幼稚園等の指示に従って手続きを行ってください。
無償化の手続きについて
無償化の対象になるためには、保護者が居住する市町村に以下の書類により申請し、無償化の認定を受ける必要があります。入園願書が配布されるときに申請書等が同封されていますので、入園手続きのときに幼稚園へ提出してください。なお、3歳未満の入園の可否については、幼稚園に直接お問い合わせください。無償化の対象になるためには利用開始前に手続きが必要です。(認定開始を希望する月の前月20日までに大和市に申請書を提出してください。)幼稚園を通じて書類を提出する際は、提出する書類を折って作成する封筒(PDF)に入れ、書類が封筒から出ないように封をして提出してください。ご提出いただいた書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をお取りください。
原則、手続きを受け付けた日から30日以内に無償化の認定結果を通知します。ただし、幼稚園等の利用の開始が4月の場合は、事務が集中して審査に時間を要するため、利用開始までに通知します。
以下の提出書類①②のうち、随時発行・取得できる書類は原則、有効期限内のものに限ります。また、認定開始希望日以前に発行された、発行日から認定開始希望日までの期間が6か月以内のものである必要があります。
①全ての方が提出する書類
|
1 |
子どものための教育・保育給付等認定申請書(PDF)/(Excel)/(記入例) | |||
| 2 | 保護者(申請者)の個人番号(マイナンバー)を確認できる以下のいずれかの書類 | |||
|
① |
マイナンバーカード(個人番号記載面)のコピー |
③ |
個人番号が記載された住民票の写し |
|
|
② |
通知カード(変更がないものに限る)のコピー |
④ |
住民票記載事項証明書 |
|
| 3 | 保護者(申請者)の本人確認ができる以下のいずれかの書類のコピー | |||
|
ⓐ |
マイナンバーカード(顔写真面) |
ⓕ |
精神障害者保健福祉手帳 |
|
|
ⓑ |
運転免許証 |
ⓖ |
療育手帳 |
|
|
ⓒ |
運転経歴証明書 |
ⓗ |
在留カード |
|
|
ⓓ |
旅券 |
ⓘ |
特別永住者証明書 |
|
|
ⓔ |
身体障害者手帳 |
|||
| 上記ⓐ~ⓘ以外の場合は、以下㋐~㋗の2つ以上の書類のコピー | ||||
|
㋐ |
健康保険被保険者証 |
㋔ |
介護保険被保険者証 |
|
|
㋑ |
後期高齢者医療被保険者証 |
㋕ |
健康保険日雇特例被保険者手帳 |
|
|
㋒ |
共済組合員証 |
㋖ |
国民年金手帳または基礎年金番号通知書 |
|
|
㋓ |
私立学校教職員共済制度の加入者証 |
㋗ |
児童扶養手当証員 |
|
個人番号確認、本人確認書類の写しの提出は、番号確認・本人確認書類(写)添付台紙兼提出物チェックリスト(PDF)を利用してください。
②世帯状況により①の書類に加えて提出する書類(下記の状況に該当しない場合は提出の必要はありま
せん。)
| 状況 | 提出書類 |
|---|---|
|
ひとり親家庭で児童扶養手当を受給していない場合 |
戸籍謄本(全部事項証明書) |
|
令和6年中又は令和7年中に国外に居住していた場合 |
国内収入と国外収入を勤務先が証明した書類 |
|
保育の必要性があり、預かり保育無償化認定を希望する場合 |
保護者の保育の必要性を証明する書類 |
申請内容に変更が生じた場合など
申請した内容に変更が生じた場合の手続きについて(幼稚園等版)
・就職により新たに保育の必要性が生じた場合、 退職により保育の必要性がなくなった場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合、市内で転居した場合など、申請した内容に変更があった場合は、 子どものための教育・保育給付等認定変更申請書 ( Excel形式)を原則、変更が生じる月の前月20日までに大和市にご提出ください。
なお、就職して新たに保育の必要性が生じた場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合などは、保育の必要性を確認できる書類を添付してください。
保育の必要性の認定は、認定に必要な書類が大和市に全て提出されて、保育の必要性を確認できた翌月からになります。
・市外に転出する場合、認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業を利用することになった場合など、無償化に関わる認定(子育てのための施設等利用給付認定)が必要なくなった場合は、子どものための教育・保育給付等認定取消届( PDF / Excel / 電子申請)を大和市にご提出ください。
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
● 電話/046-260-5640 給付審査係(幼稚園について・施設等利用費等の請求について)
● このページに関するお問い合わせはこちら