フレイル予防
フレイルとは
歳をとって、認知機能や社会的つながりを含む心身の機能が低下した状態を「フレイル」といいます。フレイルは健康な状態と介護が必要な状態の中間です。早めにフレイルに気づき、対策をすれば、健康な状態に戻すことができます。
フレイルに陥る原因は病気だけでなく、ライフイベントや生活環境の変化によることもあり、人によって様々です。
フレイル予防には「栄養」「運動」「社会参加」の3つの柱が重要になります。
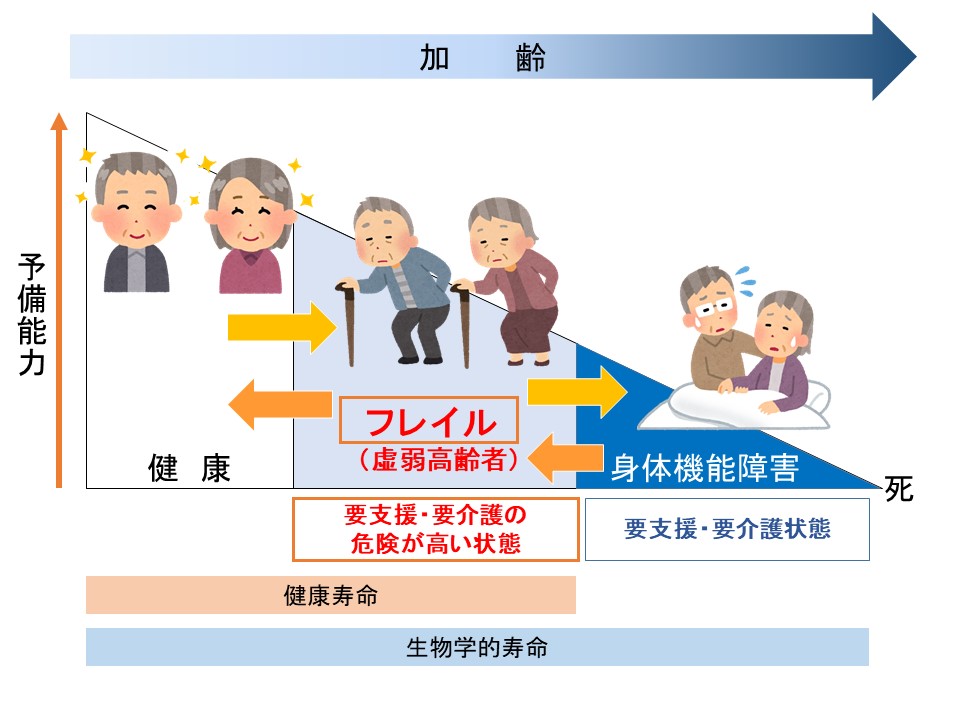
フレイルイメージ図
引用:国立長寿医療研究センターHP「フレイルに気を付けて 図2:フレイルの概念図」
フレイルチェック
まずは、フレイルかどうか確認しましょう。
後期高齢者の質問票(全15項目)
フレイルなど、高齢者の特性を踏まえて健康状態を総合的に把握する目的で、国が策定したものです。
| 類型名 | No | 質問文 | 回答選択肢 |
|---|---|---|---|
| 健康状態 | 1 | あなたの現在の健康状態はいかがですか |
|
| 心の健康状態 | 2 | 毎日の生活に満足していますか |
|
| 食習慣 | 3 | 1日3食きちんと食べていますか |
|
| 口腔機能 | 4 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか (注意)さきいか、たくあんなど |
|
| 口腔機能 | 5 | お茶や汁物等でむせることがありますか |
|
| 体重変化 | 6 | 6ヵ月間で2〜3キログラム以上の体重減少がありましたか |
|
| 運動・転倒 | 7 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか |
|
| 運動・転倒 | 8 | この1年間に転んだことがありますか |
|
| 運動・転倒 | 9 | ウォーキング等の運動を週1回以上していますか |
|
| 認知機能 | 10 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの 物忘れがあると言われていますか |
|
| 認知機能 | 11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか |
|
| 喫煙 | 12 | あなたはたばこを吸いますか |
|
| 社会参加 | 13 | 週1回以上は外出していますか |
|
| 社会参加 | 14 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか |
|
| ソーシャル サポート |
15 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか |
|
- 太字の回答選択肢に該当した場合、フレイルのリスクがあります。
- 電子申請よりご回答いただき、結果の個別案内を希望される方につきましては、別途ご連絡をさせていただきます。
こちら(e-kanagawa/外部リンク)をご利用ください。
指輪っかテスト
ふくらはぎの太さで、簡単に身体全体のおおよその筋肉量を知ることができます。
親指と人さし指で指輪っかをつくり、ふくらはぎの最も太い部分を囲みます。
人差し指が届いて、隙間ができた場合は、身体全体の筋肉量が減っている(=サルコペニア)可能性が高いと考えられます。
筋肉量が減ってきていると、フレイルになりやすいと言われています。
上記のチェックでフレイルのリスクに当てはまった方、ご家族のフレイルが心配な方などお気軽にご相談ください。
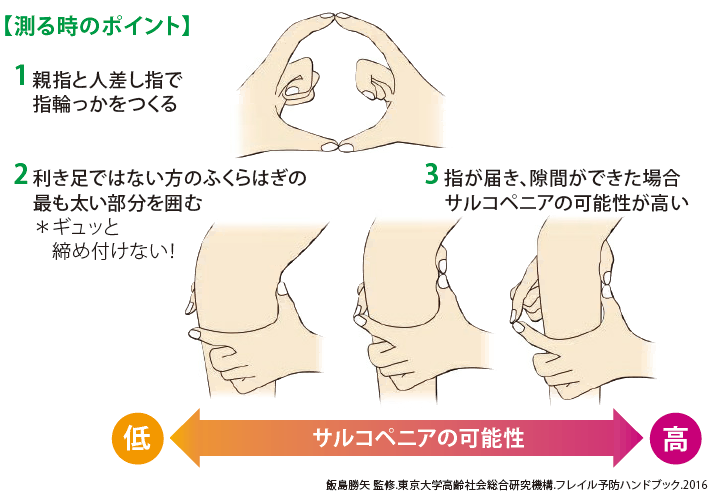
指輪っかテストイメージ図
フレイル予防活動
フレイル予防活動及び管理栄養士の保健活動はこちら
フレイルにならないための3つのポイント
フレイル予防は日々の習慣と結びついています。
栄養、身体活動、社会参加を見直すことで活力に満ちた日々を送りましょう。

関連リンク
- 厚生労働省「食べて元気にフレイル予防」パンフレット



更新日:2025年12月01日