戦中・戦後の人々の生活の様子(2)
昭和16年(1941年)頃~終戦

農繁期共同炊事
農繁期の労働力不足を補うため実施されました。

農繁期共同炊事
献立表に「昼はきんぴら、夜はごった汁(ご飯はなし)」とあります

脱穀
昭和16年秋収穫した米の脱穀見学

開墾
つきみ野の目黒川沿いにあった田は谷戸田と呼ばれ、そこを開墾するにあたり、山形県からの移動労働力を頼みました。

籾すり作業

家族
出征した兵士に送った家族の写真

炭焼き準備
炭焼き用の木を伐採するため公所の集落の人たちが谷戸田に集まったところ。

漬物
戦時中に国策に応じた食糧増産・国家的統制を目的とした農協の前身、農業会が設立されたが、その農業会で大根を漬物にしている作業風景。

家族
殻が飛ばないようにムシロをかぶせた動力式脱穀機を囲んで

家族
戦争により働き盛りの男性が戦地に行ってしまっている厳しい時代でした。
「大和写真館」および「大和写真館2」より
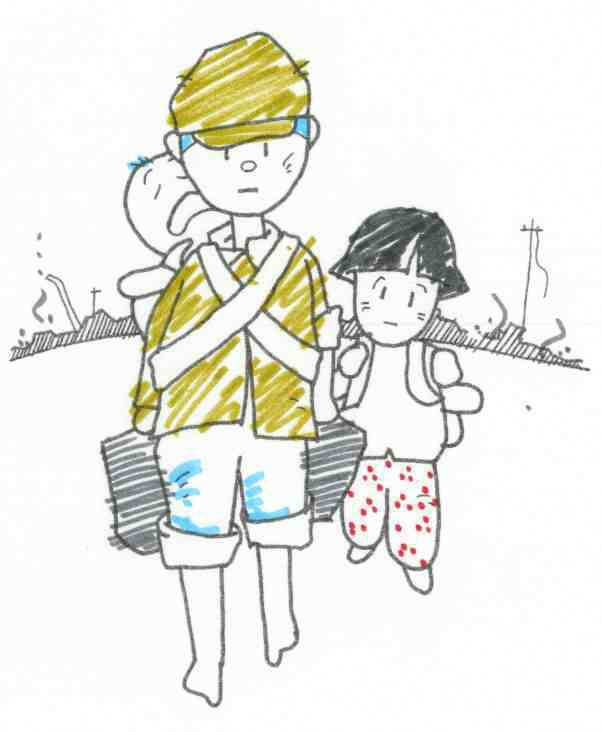



更新日:2022年02月01日