学童疎開(1)


高坂国民学校の疎開寮位置図
学童疎開の経緯
1941年(昭和16年)、小学校は国民学校と呼ばれ、その頃の中等学校以上では、軍事教練が授業の中に入り、工場等で働く学徒動員がされるようになりました。1942年には、東京、名古屋、神戸など米軍機による本土初の空襲を受け、また同年ミッドウェー海戦での大きな打撃を被り、更に、翌年にはガダルカナル撤退を余儀なくされた日本軍は、制空権、制海権を失い、次第に戦況の敗色濃厚となっていきました。その中、日本政府は、1944年(昭和19年)「一般疎開促進要綱」、「学童疎開促進要綱」、「帝都学童集団疎開実施要領」の閣議決定がされ、縁故疎開ができない国民学校初等科三年から六年までの児童を対象に学童集団疎開が実施されることになりました。
大和市と学童疎開
縁故疎開ができない児童を対象に集団疎開が実施され、神奈川県の疎開については、当時の近藤壌太郎県知事の判断で、県内への疎開を原則とする方針が出され、それを受け大和市(旧大和町・旧渋谷村)では、横須賀市の高坂・長浦国民学校の児童を受け入れました。
疎開の経過
高坂国民学校(現、西浦賀町3-150高坂小学校)では、1944年7月15日の教務会で学童集団疎開に関する検討が初めて行われ、翌日には早速に父兄会が開催されて学童疎開についての説明と参加希望の調査が行われました。その結果、学童集団疎開の受け入れ予定数7,500人に対して約10,000人の希望があったため、縁故疎開の勧誘を行ったうえで、8月1日に集団疎開を希望する保護者を集めて父兄会が開催されて、最終的な説明が行われました。8月8日には全校児童に説明し、8月17日には疎開先の大和町に先発隊として8人の教員が出発しました。この日の午後2時からは、大和国民学校において、大和町助役の八木保隆氏の司会で、地元の町内会長、部落長、農事実行組合長と、先発した高坂国民学校教員との間で、疎開児童受け入れをめぐる懇談会が開催され、さらに宿舎別の協議会が行われました。このようにあわただしい準備期間を経て、8月21日に学童集団疎開の一行が大和町に到着しました。
高坂国民学校大和町疎開分団
疎開児童162名(男子100名、女子62名)の集合写真
背景は、児童が通学した大和国民学校の校舎

7つの寮
7寮のうち4ヶ所は寺院、松風寮は南林間にあった大和学園の寄宿舎、下草柳寮と深見寮は地域の集会施設をそれぞれ借用したものです。このうち松風寮は、面積・児童数ともに最も規模の大きい寮でしたが、敗戦後の1945年8月25日に鶴林寺寮に合併されました。また下草柳寮は同年8月2日に観音寺寮と合併、善徳寺寮も同年9月3日に定方寺寮と合併し、最終的に5寮に再編成されました。
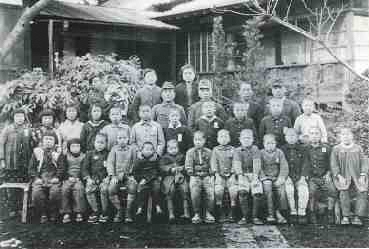
定方寺寮
所在地 下鶴間145
建物概要 木造平屋トタン・草葺き
総坪数 124.9
使用坪数 27.5
疎開当初の児童数 計18
男 15 女 3
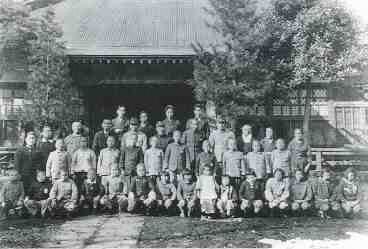
観音寺寮
所在地 下鶴間2240
建物概要 木造平屋トタン・草葺き
総坪数 122.5
使用坪数 73
疎開当初の児童数 計20
男 13 女 7

鶴林寺寮
所在地 下鶴間1938
建物概要 木造平屋トタン・草葺き
総坪数 85.5
使用坪数 25
疎開当初の児童数 計16
男 9 女 7
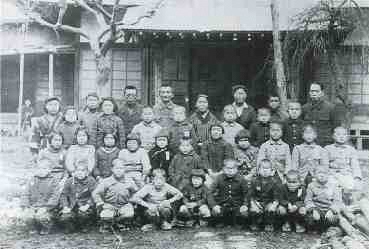
善徳寺寮
所在地 上草柳971
建物概要 木造平屋トタン葺き
総坪数 79
使用坪数 26
疎開当初の児童数 計26
男 16 女 10
松風寮
所在地 下鶴間3245
建物概要 木造2階トタン葺き
総坪数 63.25
使用坪数 63.25
疎開当初の児童数 計51
男 26 女 25
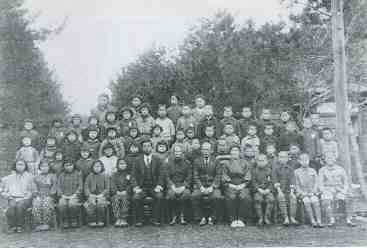

深見寮
所在地 深見島津896
建物概要 木造平屋トタン葺き
総坪数 16.5
使用坪数 16.5
疎開当初の児童数 計9
男 7 女 2
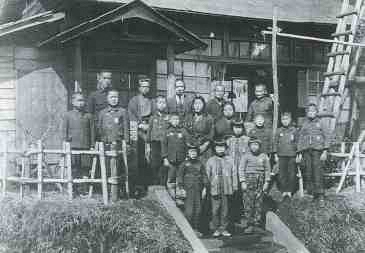

下草柳寮
所在地 下草柳858
建物概要 木造平屋トタン・草葺き
総坪数 40
使用坪数 40
疎開当初の児童数 計22
男 14 女 8

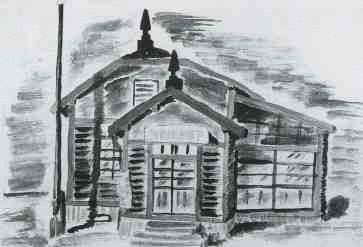



更新日:2023年03月20日