学童疎開(2)
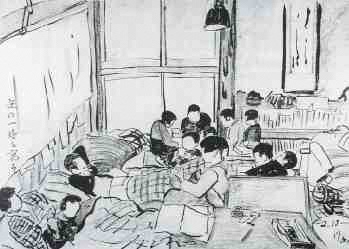
疎開先での生活
児童たちが大和国民学校へ初登校したのは1944年8月28日で、授業は地元の児童とは別に行われました。そのため二部授業となり、地元児童と疎開児童は1ヶ月ごとに午前、午後を交替していました。
疎開児童たちは、授業がない時間には近所の農家の手伝いに出かけていました。手伝いに行った先の農家でお礼に食事をご馳走になったり、おやつをもらったりするのが大きな楽しみだったようです。
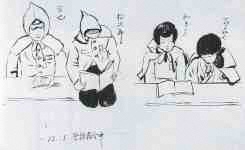
1944年11月頃になると、警戒警報・空襲警報が頻繁に発令されるようになり、登校せずに寮で授業を行うことが多くなったようですが、同月14日には158名の児童が参加して、相模国分寺跡から相模川までの遠足が行われています。

疎開先での食生活
食糧はもちろん配給制で、米や副食品などは下鶴間と大和にあった配給所や地元の商店(屋号は大矢、榎本、高下、清水など)に、子供たちが分担して取りに行っていたようです。時には、茅ヶ崎の高座郡食料品配給統制組合や藤沢市方面まで配給品の受給に出かけることもありました。
野菜類は地元の農事実行組合が供出を請負ましたが、定方寺寮、観音寺寮、鶴林寺寮、深見寮、善徳寺寮などは地域に農家が多かったために、予定した供出量はほぼ確保できたようです。一方で松風寮や下草柳寮は、地元からの供出だけでは賄いきれず、市場に頼るなど調達には苦労したようです。

定方寺寮では疎開当初は配給の米が余ったほどだったが、ここから下草柳へ転寮した児童は途端にひもじい思いをしたとの証言もあります。寮によって食糧事情は相当に異なっていたようです。
配給の米に代わって豆粕や干し芋が混じるなど質が低下し始めたのは1945年の4月頃からだったといいます。
深見寮では、農作業の経験がない児童と先生が畑を開墾して、ほうれんそうなどを作付けしたり、借用した2反の畑に麦を蒔いたりして食糧の自給に務めました。

疎開先での娯楽
寮では、児童や先生たちによる演芸会がしばしば開催されました。時には貰い風呂などで世話になっている地元の人たちを招いて開催されることもあり、大いに賑わったようです。演芸会は児童たちの最大の娯楽であると共に、歌や遊戯の練習などで忙しく過ごすことによって、望郷の念を消し去る手段ともされたようです。

宿泊日記
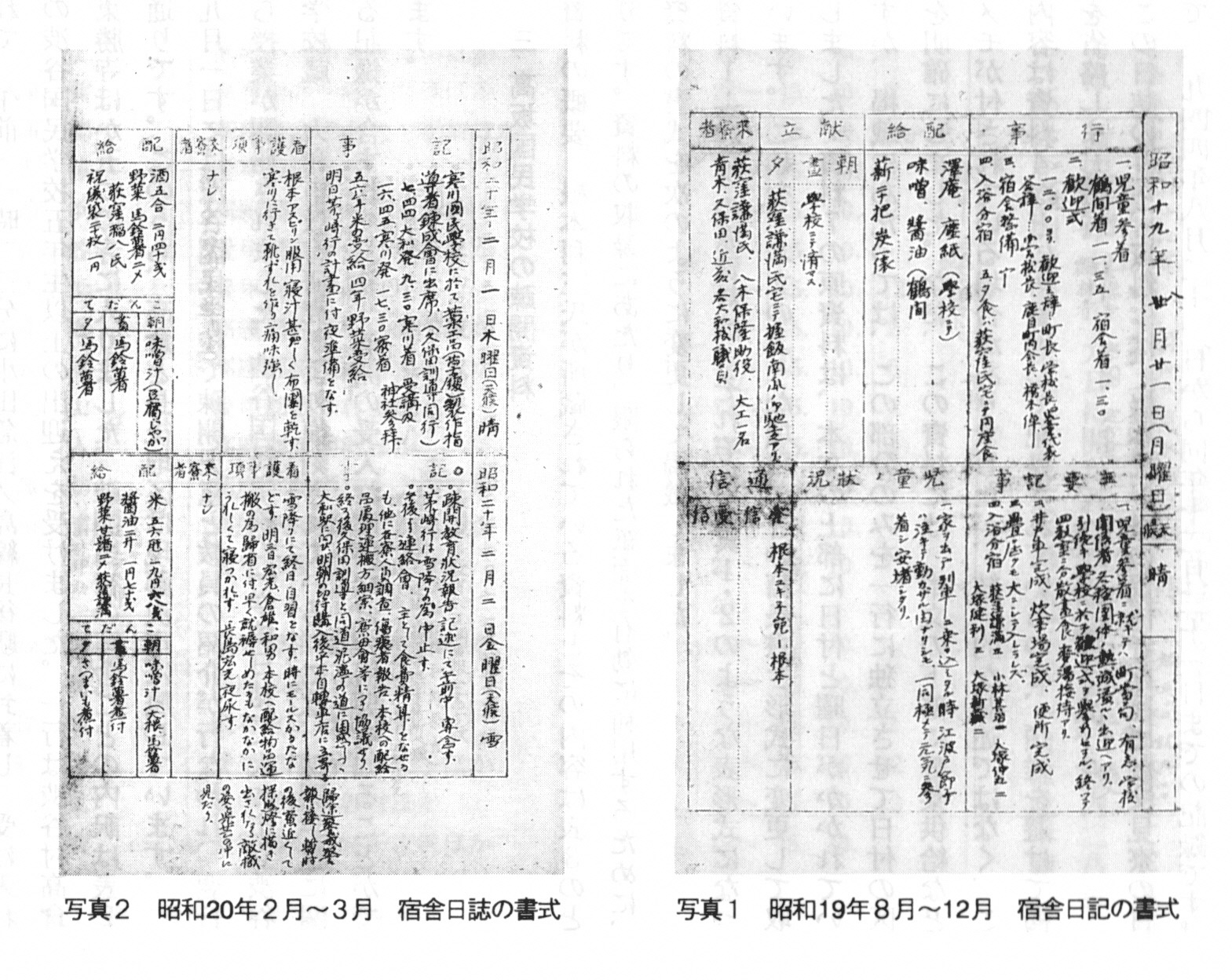
疎開経験者の窓
疎開経験をお持ちの3人の話を聞くことができます。(機種により聞き取りにくい場合がありますが、ご容赦ください。)
映像や音声をご利用いただくには、Windows Media Playersが必要です。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして入手してください。(無料)
元訓導 根本 利三氏(大正3年生まれ、当時30歳)
横須賀市の高坂国民学校の訓導として、児童たちを引率してきた。
学童疎開の児童たちとともに1年1ヶ月余を大和の地で過ごした。根本氏は、
疎開当時は児童9人と共に深見寮で生活し、翌年4月からはj定方寺寮に移
って責任者を務めた。
元寮母 渡部 キハ氏
大和市下鶴間(公所)出身、定方寺寮にて奉職
元学童 堀 久子氏
疎開当時4年生(10歳)、定方寺寮へ疎開




更新日:2022年02月01日