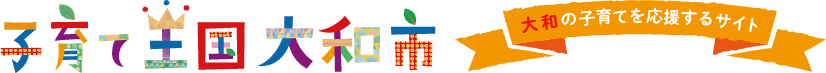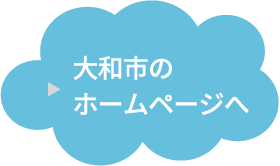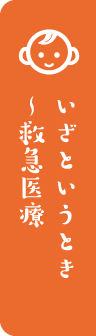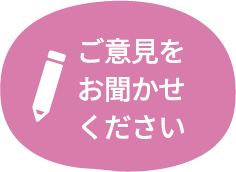特別児童扶養手当
知的または精神、身体に政令で定める以上の障がいを有する20歳未満の子を育てる保護者に、手当を支給します。
注意!
「特別児童扶養手当」と似た名前の手当で「児童手当」と「児童扶養手当」があります。「児童手当」は、対象となる子を養育している人に支給されるものなので、二人親世帯・一人親世帯いずれも受給することができます。 詳しくは、「児童手当」の項目をごらんください。
また、「児童扶養手当」は、一人親世帯(または養育者)の生活の安定と、お子さんの健全な育成に寄与することを目的に支給される手当です。 詳しくは、「児童扶養手当」の項目をごらんください。
重度の障がいがある場合は、「障害児福祉手当」が受けられる可能性がありますので、詳しくは、「障害児福祉手当」の項目をごらんください。
支給対象
精神、知的または身体に、政令で定められた中程度以上の障がいがある20歳未満の子の保護者に、手当を支給します。対象児童を監護するもののうち、生計の中心者(最多収入者)が請求者となります。
所得制限
受給には所得制限があります。請求者と配偶者、さらにそのほかの生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、次の計算式に当てはめたときに、一定以上の所得額があると支給は受けられません。
計算式
所得額=年間の収入金額-必要経費-80,000-地方税法で控除を受けたもの
※ 年間の収入が給与収入のみの場合は、(年間の収入金額-必要経費)の額は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」となります
※ 地方税法で控除を受けたもののうち、対象となるのは次の控除です。
・請求者本人の場合
障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は、いずれも控除相当額
・配偶者・生計を同じくする扶養義務者
障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、老人扶養控除6万円、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は、いずれも控除相当額
計算式で算出された所得額が、次の表の限度額未満であること
| 税法上で扶養した親族等の人数 | 請求者本人の所得限度額 | 配偶者および 扶養義務者の所得限度額 |
|---|---|---|
|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
|
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
|
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
|
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
|
4人 |
6,116,000円未満 |
7,175,000円未満 |
※ 請求者本人の控除に、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、所得限度額に25万円を加算します。また、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき所得限度額に10万円を加算します。
※ 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき所得限度額に6万円を加算します(扶養している親族がすべて老人扶養親族の場合は、2人目から加算されます)。
支給内容(手当額について)
・重度障害児1人につき月額56,800円(手当等級1級 令和7年4月現在)
・中度障害児1人につき月額37,830円(手当等級2級 令和7年4月現在)
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
※手帳と手当等級とは一致しない場合があります。
|
支払日 |
11月11日 |
4月11日 |
8月11日 |
|---|---|---|---|
|
支給対象月 |
8月~11月分 |
12月~3月分 |
4月~7月分 |
申請方法
次の物を用意し、障がい福祉課窓口へお越しください。
① 請求者と対象となる20歳未満の子の情報が記載された戸籍謄本または抄本
※戸籍謄本は、戸籍に記載されたすべての人の情報が記載されたものです。戸籍抄本は、戸籍に記載された一人のみの情報となります。
② 対象となる20歳未満の子の障害の程度が分かる医師の診断書
※障がい福祉課に、診断書の所定の書式があります。
※次の場合は、医師の診断書の提出を省略できる場合があります。
・視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障害で、概ね1~3級の身体障害者手帳を所持している場合
・療育手帳A1またはA2を所持している場合
③ 請求者名義の預金通帳
④ 請求者、対象となる20歳未満の子、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できる物(通知カード、マイナンバーカードなど)
⑤ 本人確認書類(請求者以外の方が申請をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)
※次の物はいずれか1つ
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署から発行・発給された書類で、適当と認められるもの。
※次のものは2つ以上の書類で本人確認が可能なもの
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険等被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保
⑥ 請求者と対象となる20歳未満の子が別居している場合は別居監護申立書
※別居監護申立書の取得方法などは、障がい福祉課へお問い合わせください。
毎年必要な手続き
受給資格の認定を受けた方は、年に1度、所得状況届の提出が必要になります。届出期間を過ぎて手続きした場合、手当の支給が遅れることがあります。また、未提出のまま2年が経過すると、「手当を受ける権利」が無くなります。
届出期間:8月12日~9月11日(原則)
その他必要な書類は、市からお知らせします。
障がいの程度により必要な更新の手続き
障がいの程度により、一定の期間ごとに医師の診断が必要となります。市から再診の手続きに関するお知らせが届きましたら、医師に診断書を作成してもらい、再診(有期更新)届と合わせて提出してください。
各種変更届
住所や氏名、家族構成などや、すでに届け出た所得が修正申告などによって変更となった場合は、速やかに変更届を提出してください。また、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更となったときも、手当の等級が変わることがありますので、速やかにご相談ください。
資格喪失届
対象となる20歳未満の子が施設に入所した場合や、手当を受けている保護者が監護または療育をしなくなったときは、資格喪失届を提出する必要があります。受給資格を失ったあとに受け取った手当は、返還しなければならないため、ご注意ください。
【お問い合わせ】
● あんしん福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(保健福祉センター5F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5665 FAX/046-262-0999
● このページに関するお問い合わせはこちら