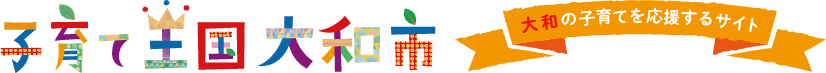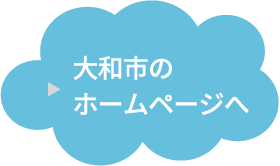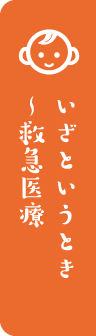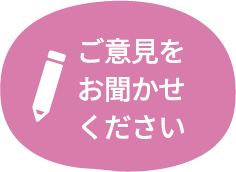予防接種(定期予防接種)
赤ちゃんは、病気に対する抵抗力(免疫)をお母さんから分けてもらい、生まれてきます。しかしその力は、生後3~8か月程度で消えてしまいます。あとは赤ちゃん自身の力で免疫をつけなくてはいけませんが、その助けとなるのが予防接種です。
予防接種は、毒を弱めた細菌などから作った「ワクチン」を体内に投与し、それと闘うことによって身体の中に病気に対する抵抗力(免疫抗体)をつける方法です。
予防接種の対象になる病気のほとんどは感染症です。予防接種には、接種を受ける子ども自身の健康を守るだけでなく、周りの人への感染を防ぎ、地域・社会全体でその病気が流行するのを防ぐ効果があります。
出生届を出した方に郵送する冊子「予防接種と子どもの健康」や市からのお知らせなどを読んでいただき、予防接種の必要性や副反応などについて理解のうえ、予防接種を受けてください。
※ このページでは予防接種法に基づく定期予防接種をご案内しています。おたふくかぜ、子どものインフルエンザなど、予防接種法に規定されていない予防接種(任意予防接種)については、各医療機関へ直接お問い合わせください。
対象者
大和市の住民基本台帳に記録されている方、または出入国管理及び難民認定法の規定により仮放免され、大和市に居住している方が対象になります。
また、外国籍の方で在留資格の申請手続きがお済みでない方は、対象とはなりません。在留カードの期限が切れていないか、ご確認をお願いいたします。
※ 転出日当日は、すでに転出し、大和市民ではなくなったものとみなされるため対象となりません。この日以降の接種については、転出先の自治体にお問い合わせください(接種した場合は全額自費となります)。
接種できる医療機関
【市内】予防接種・健康診査 協力医療機関名簿、 【市外】予防接種・健康診査 協力医療機関名簿 に記載してあるいずれかの協力医療機関で接種してください。これ以外の医療機関で接種した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。なお、やむを得ない事情により、協力医療機関での接種ができない場合は、事前に医療健康課へお問い合わせください(市からの依頼書が必要となる場合があります)。
予防接種を受けるために必要な書類の交付について
大和市に出生届を出した方
生後2か月になる前に、次の6種類の書類を郵送します。
(このほかに、4か月健康診査の日程と診査票も同封しています)。
① 大和市予防接種予診票冊子
② 「予防接種と子どもの健康」冊子(全国共通)
③ 予防接種スケジュール
④ 大和市予防接種・健診番号シール(バーコード)
⑤ 大和市乳幼児予防接種・健康診査、協力医療機関一覧
※ 大和市予防接種予診票冊子に含まれない、「日本脳炎」「2期麻しん風しん」「2期ジフテリア破傷風」の予防接種の予診票については、適時送付します。
大和市に転入してきた方(7歳6か月未満)
① 窓口での手続き(接種期限が迫っているなど、お急ぎの予防接種がある方はこちら)
親子健康手帳(母子健康手帳)を持参してください。その場で大和市予防接種・健診番号や予診票などの書類をお渡しします。
※窓口で予防接種歴などを所定の用紙に記入していただきます。
[窓口]医療健康課
保健福祉センター 4F(大和市鶴間1-31-7)
受付時間:平日8:30~17:00
② 郵送での手続き
転入届を出された翌月に、予防接種歴をお伺いする書類と返信用封筒を市から郵送します。必要事項を記入し、返送してください。大和市予防接種・健診番号や予診票などの書類を郵送します。
※7歳6か月以上20歳未満で転入された方の予防接種については、医療健康課へお問い合わせください。
予防接種と対象年齢
・ロタウイルス予防接種(経口生ワクチン)
2種類のワクチンがあり、いずれかのワクチンを接種するかで接種時期が異なります。
・ロタリックス:生後6週~24週
・ロタテック:生後6週~32週
・B型肝炎予防接種(不活化ワクチン)
1歳未満。標準的な接種期間は、生後2か月~9か月未満
・小児用肺炎球菌予防接種(不活化ワクチン)
生後2か月~5歳
・5種混合予防接種(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)(不活化ワクチン)
生後2か月~7歳6か月未満
・4種混合予防接種(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)(不活化ワクチン)
※すでに4種混合ワクチンで接種を開始している場合
生後2か月~7歳6か月未満
・ヒブ予防接種(不活化ワクチン)
※すでにヒブワクチンで接種を開始している場合
生後2か月~5歳
・2種混合予防接種(ジフテリア、破傷風)(不活化ワクチン)
11歳以上13歳未満
・麻しん風しん予防接種(生ワクチン)
1期:1歳~2歳未満(1歳以降、できるだけ早めに接種しましょう)
2期:幼稚園・保育園の年長にあたる、5歳~7歳未満(就学前)の子で、4月1日から翌年の3月31日までの間
・水痘(水ぼうそう)予防接種(生ワクチン)
1歳~3歳未満
・BCG(結核)予防接種(生ワクチン)
生後3か月~1歳未満。標準的な接種期間は、生後5か月~8か月未満
・日本脳炎予防接種(不活化ワクチン)
1期:生後6か月~7歳6か月未満
※ 生後6か月から接種は開始できますが、標準的には3歳からの接種となっています。
2期:9歳~13歳未満
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防)(不活化ワクチン)
小学校6年生~高校1年生相当の女の子
※ 長期療養等により定期予防接種が受けられなかった方へ
定期予防接種の対象年齢の期間内に、長期にわたる療養等により予防接種が受けられなかった場合は、治癒後2年までの間、定期予防接種として接種することができます。この制度には、対象となる疾病の基準があるため、接種前に申請が必要となります。詳細については、医療健康課へお問い合わせください。
予防接種を受ける時の持ち物
① 親子健康手帳(母子健康手帳)※紛失した方はこちらをご確認ください
② 受ける予防接種の予診票
③ 大和市予防接種・健診番号(バーコード)
予防接種を受ける前と後の注意事項
接種前
① 予防接種は体調のよいときに受けるのが原則です。少しでも熱のあるとき、かぜぎみのとき、食欲のないとき、ふだんと様子が違うときなどは、無理をせず、次の機会に接種してください。
② 受ける予定の予防接種は、お送りした「予防接種と子どもの健康」の冊子や市からのお知らせをよく読み、必要性や副反応について理解してください。分からないことは、受ける前に接種する医療機関の医師に相談してください。
③ 親子健康手帳(母子健康手帳)は必ず持参してください。
④ 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。
⑤ 子どもの予防接種は保護者同伴での接種が原則です。保護者が同伴できない場合は、日ごろからお子さんの健康状態の分かる親族でも同伴できますが、保護者からの委任状が必要になります。詳細については、医療健康課へお問い合わせください。
〇委任状書式 PDF形式 / 【記入例(PDF)】
接種後
① 予防接種を受けた後、30分程度は医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
② 接種当日は、はげしい運動は避けましょう。
③ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴はさしつかえありませんが、接種部位をこすることはやめてください。
④ 注射生ワクチン(※)の接種から、ほかの種類の注射生ワクチンの接種までは4週間以上の間隔をあけてください。
⑤ 接種した部位の発赤や腫れや痛み、軽いだるさ、頭痛、発熱、寒気などが起こることがありますが、通常2~3日でよくなります。ただし、これらの症状が異常に強いときは、医師の診察を受けてください。
※生ワクチン…生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの。これを接種することで、その病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)ができます。
【お問い合わせ】
● 健幸・スポーツ部 医療健康課(保健福祉センター4F) 健康診査・がん・感染症予防係
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5662
● このページに関するお問い合わせはこちら