限度額適用認定証(国民健康保険)
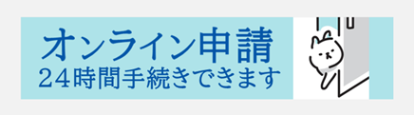
このページに記載されている手続きの一部は、オンラインでの申請が可能です
国民健康保険の限度額適用認定証は、保険年金課窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで交付申請が可能です。手続方法の詳細については下記をご参照ください。
※オンライン申請の場合は、マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)から手続してください。
≪アクセス方法≫
- マイナポータル(ホーム) または 「さがす」メニューで、自治体を「神奈川県 大和市」に設定
- 「さがす」メニューのキーワード検索で「国民健康保険」「国民年金」「後期高齢者医療」などの制度名を入力 (「カテゴリから検索」でも選択できます)
限度額適用認定証とは
医療機関等に提示することで、月の自己負担額を自己負担限度額までにする証です(高額療養費制度は、還付までに3か月以上を要します。限度額適用認定証を使用することで、医療機関での自己負担額が自己負担限度額までとなります)。
マイナ保険証(または資格確認書)を利用し、自己負担限度額の区分についてオンライン資格確認を受ければ、外来でも、入院でも、個人単位でいち医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までになりますが、オンライン資格確認を受けられない事情がある場合などは、受診の前に限度額適用認定証をご申請ください。
(注意)
- 複数の医療機関等を受診する場合は、医療機関ごとに限度額適用認定証を提示し、医療機関ごとにいったん自己負担限度額までお支払いください。その後、医療機関等で支払った自己負担額を月ごとに保険者(大和市)で集計し、自己負担限度額を超えた場合には高額療養費の請求についてお知らせする通知書(申請書)を世帯主へお送りします。詳しくは、高額療養費のページをご参照ください。
- 国民健康保険税を滞納していると、限度額適用認定が受けられない場合があります。
高額療養費について
高額療養費については以下のページをご確認ください。
高額療養費の計算例(70歳以上の人と70歳未満の人との世帯)
自己負担限度額について
自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく医療費の上限額です。被保険者の年齢、及び前年の所得と医療費によって異なります。
| 所得区分(※) | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 所得901万円超(ア) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 所得600万円〜901万円以下(イ) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 所得210万円〜600万円以下(ウ) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 所得210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(※)毎年8月1日に、その年度の所得(基礎控除後の総所得金額等)で判定します。また、世帯の被保険者の状況や所得に変更があった場合は、再判定を行います。
同じ国保世帯で、その月を含め過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から4回目以降の欄内の限度額を超えた分が支給されます。
| 所得区分(※) | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【 140,100円 】 (注釈1) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【 140,100円 】 (注釈1) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【 93,000円 】 (注釈1) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【 93,000円 】 (注釈1) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【 44,400円 】 (注釈1) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【 44,400円 】 (注釈1) |
| 一般 | 18,000円 (注釈2) | 57,600円 【 44,400円 】 (注釈1) |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(※)毎年8月1日に、その年度の住民税課税所得で判定します。また、世帯の被保険者の状況や住民税課税所得に変更があった場合は、再判定を行います。
住民税課税所得は、収入金額から給与所得控除、公的年金等控除、必要経費などを差し引いて求めた総所得金額等から、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの各種取得控除を差し引いて算出されます。
- 一般・・・現役並み所得者、低所得者2、低所得者1 以外の人
- 低所得者2・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
- 低所得者1・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円)として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人
(注釈1) 過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は【 】(括弧)の額
(注釈2) 年間限度額144,000円
限度額適用認定証の申請について
申請方法
大和市役所保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により交付申請してください。
- 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
- 郵送での申請を希望される場合で、印刷環境がない場合には申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。
- オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 88.9KB)
(注意)
- 限度額適用認定証は国民健康保険税に未納のない人に発行しています(国保税に未納がある場合は、事前に納付相談が必要です)。
- 自己負担限度額の区分が「一般」の人、「現役並み所得者3」の人は、医療機関の窓口で自己負担限度額が適用されるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。申請の要否について確認したい場合は、電話もしくは窓口でお問い合わせください。
- 発行の際には収入の確認が必要なため、転入等により大和市で収入がわからない人には所得証明書の提出をお願いすることがあります。
- 月の半ばで保険者が変わった場合(他の市町村に転出入した場合や職場の保険などに変わったときなど)は、それぞれの保険者で計算になります。
- 有効期限(最長で毎年7月31日まで)後も限度額適用認定証が必要な場合は、有効期限後に改めて申請が必要です。
- 保険年金課窓口で別世帯の人が手続きされる際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払が免除されます
マイナ保険証でオンライン資格確認を受ければ、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細については以下のページをご確認ください。
食事代と長期入院の認定について
以下の人は、入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
- 70歳未満で所得区分が「オ」
- 70歳以上75歳未満で所得区分が「低所得者1」もしくは「低所得者2」
大和市役所保険年金課窓口または郵送で交付申請してください。
また、上記の人のうち申請月から過去12か月以内に90日以上入院している場合は、長期入院の認定を受けることで、91日目以降の入院時の食事代が更に下がります。
長期入院の認定の申請方法
≪窓口で申請する際に必要なもの≫
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- (あれば)交付対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 限度額適用認定証(既に交付を受けている場合のみ)
- 91日以上入院していることがわかる領収書(食事の負担額が記載されていて、領収印が押されているもの)
- 長期入院の認定に係る入院日数の対象となるのは、住民税非課税世帯である期間中の入院で、かつ申請を行った月以前の12か月以内となります。入院開始日および最終退院日ではありません。長期入院の認定および食事差額の請求はお早めにご申請ください。
- 食事代の詳細については以下のページをご確認ください。
- 郵送での申請を希望される場合は、申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。
- 有効期限(最長で毎年7月31日まで)後も限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な場合は、有効期限後に改めて申請が必要です。
- 保険年金課窓口で別世帯の人が手続きされる際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。



更新日:2025年08月01日